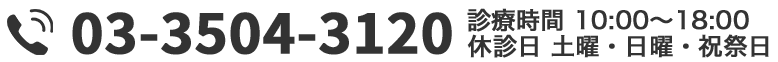
水を含むと歯痛が治るのはなぜ?原因と放置の危険性を解説
冷たい水を含むと歯の痛みが一瞬で和らぐ経験をしたことがある方は多いのではないでしょうか。
水で痛みが落ち着くのは一時的な現象にすぎず、原因を放置すれば症状は悪化し、最悪の場合は抜歯に至ることもあります。
本記事では、水で歯痛が和らぐ仕組みや考えられる原因、放置するリスクについて詳しく解説します。
大切な歯を守るために、ぜひ参考にしてください。
水を口に含むと歯痛が治る理由
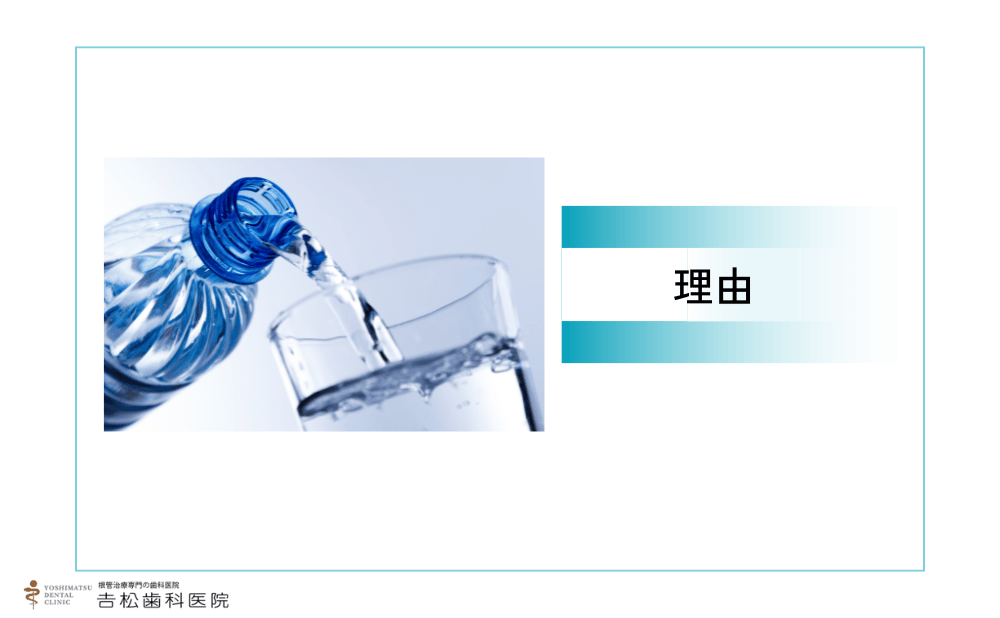
水を口に含むと歯痛が治る理由は下記のとおりです。
- 口の中が冷やされるため
- 口内の炎症を一時的に抑えるため
それぞれ説明します。
口の中が冷やされるため
冷たい水を口に含むと、一時的に歯や歯ぐきの温度が下がり、痛みが和らぐことがあります。
虫歯が進行して歯髄炎を起こしている場合、炎症によって歯の内部の圧力が高まり痛みを感じやすくなります。
そこに冷水が触れることで神経が一時的に麻痺し、痛みが軽減されるのです。
この作用は鎮痛剤のような根本治療ではなく、あくまで一時的な「冷却効果」によるものです。
口内の炎症を一時的に抑えるため
炎症がある部位に冷水が触れると血流が抑えられ、腫れや熱感が軽減されることがあります。
これは体の他の部位を冷やすと腫れが引くのと同じ仕組みです。
しかし、冷水で得られるのは一時的な炎症の緩和にすぎません。
原因となる虫歯や感染を取り除かなければ、再び痛みは現れ、むしろ症状が悪化する危険性もあります。
歯痛の症状が出る原因

歯痛の症状が出る原因は次のとおりです。
- 虫歯の進行による歯髄炎
- 歯のひびや欠け
- 歯周病
順番に解説します。
虫歯の進行による歯髄炎
虫歯が進行すると歯の神経に細菌が到達し、歯髄炎が起こります。
この段階になると冷たい水がしみたり、逆に水を含んだときに痛みが一時的に治まるといった症状が現れます。
これは神経にも症状が出ているサインであり、放置すれば神経が壊死して強い痛みや膿の形成につながります。
吉松歯科医院ではマイクロスコープを使った神経を残す虫歯治療を行っています。
詳しくは以下をご確認ください。

歯のひびや欠け
見た目には小さなひびや欠けでも、そこから細菌が侵入して内部に炎症を起こすことがあります。
冷水がひびの内部に触れると痛みが和らぐこともありますが、根本的な解決にはなりません。
歯の破折は放置すると保存が困難になるケースが多いため、早期発見と治療が必要です。
歯周病
歯ぐきや歯を支える骨が炎症を起こす歯周病も歯痛の原因となります。
歯周病が進行すると歯ぐきに膿が溜まり、痛みや違和感を引き起こします。
歯周病は自覚症状が出にくいため、違和感が続く場合は必ず歯科医院で検査を受けましょう。
吉松歯科医院の歯周病治療について詳しくは下記をご覧ください。

歯痛の症例紹介
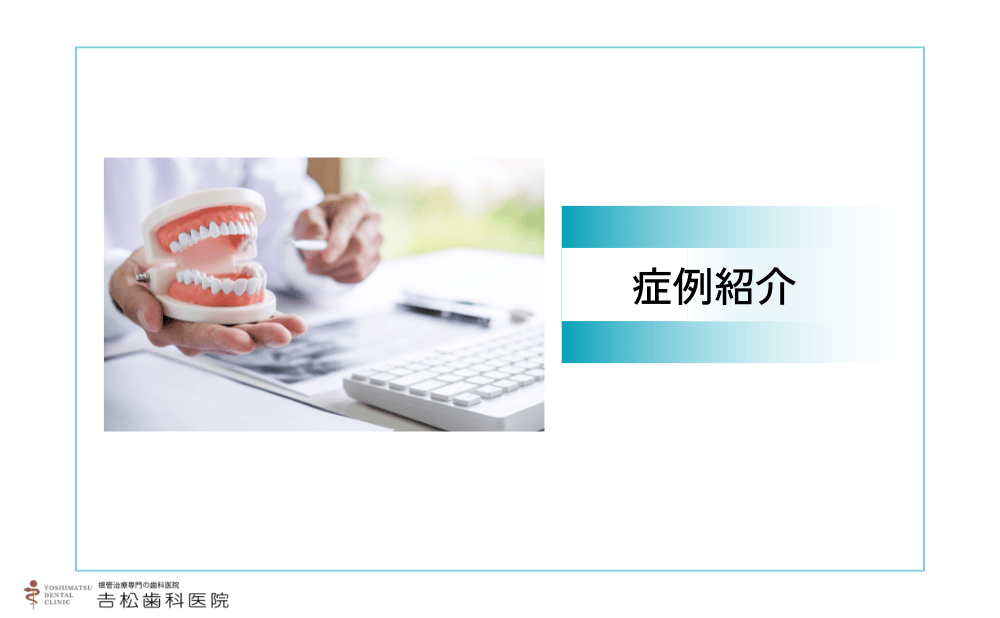
標準的な診断基準では、打診痛、温かいものでしみるなどの症状があると神経、歯髄を取る治療、抜髄が必要になります。
しかし現在はマイクロスコープ、接着歯学、MYAに代表されるバイオセラミック系材料があるため、感染している一部の歯髄を取り除き、健全だと思われる歯髄を残し保存する治療方法が試みられています。
小児の治療では、断髄という方法は以前より存在するのですが、成人で断髄をするというのはこの10年で試みられている方法です。
そのため吉松歯科医院では抜髄という治療は数年に1度ある程度の治療方法になっています。可能な限り自分の神経を残す、歯髄を残すという治療方針のためです。
私が修業時代に教えてもらった日本の歯内療法の祖である大谷満先生(故人)以前より、”歯髄に勝る根管充填材はない”とおっしゃってました。
吉松歯科医院では抜髄と診断された歯牙でも神経、歯髄を残す事を10年前より行なっています。
【動画解説付き・症例1】断髄症例
30代女性、上顎右側第一小臼歯、自発痛、打診痛があり、歯髄炎と診断し、コンサルテーション後、抜髄の処置で対応することに。
しかし、治療当日患者さんに神経を残す治療の長所、短所、特に急に痛くなる可能性の話をして神経を残す治療に処置内容を変更して断髄処置を行いました。
麻酔をしてラバーダムアイソレーションを行い、グリーン色に染まるう蝕検知液を用いて丁寧に軟化象牙質、感染部の除去を行うと神経、歯髄と交通しており、歯髄が露出して一部を次亜塩素酸にて融解して同日にコンポジットレジンにて修復して現在、症状は良くなっております。
歯痛治療後のメンテナンス
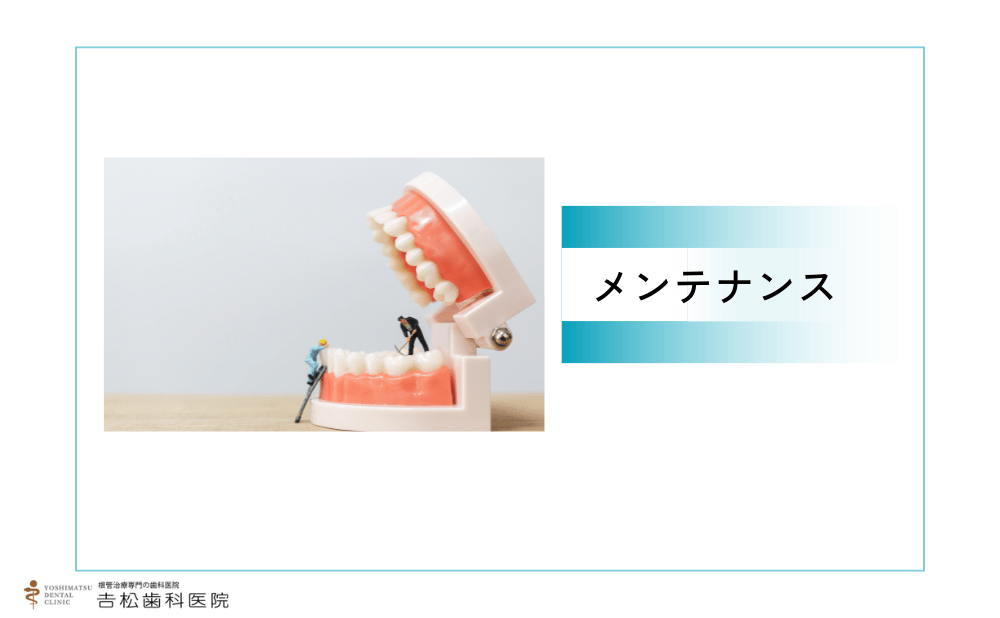
歯痛治療後のメンテナンスについて詳しくは下記のとおりです。
- 日常のセルフケア
- 定期検診の受診
- 噛み合わせや被せ物の調整
それぞれ解説します。
日常のセルフケア
根管治療をした歯は、一度感染した経緯があるため、再発のリスクが高くなります。
そのため、毎日のセルフケアが欠かせません。
正しいブラッシングの方法を意識することはもちろん、歯と歯の間に残る汚れを落とすためにはデンタルフロスや歯間ブラシの併用が効果的です。
また、食後はなるべく早めに口腔内を清掃し、細菌が繁殖する時間を与えないことが重要です。
こうした習慣を続けることで、治療後の歯を長持ちさせ、口全体の健康を守ることにつながります。
定期検診の受診
痛みがないからといって歯科医院から足が遠のくと、気付かないうちに虫歯や歯周病が進行してしまう危険があります。
これらは初期段階ではほとんど自覚症状がなく、発見が遅れると治療が大掛かりになり、費用や時間も膨らみます。
そのため、症状がなくても半年に一度は定期検診を受けることをおすすめします。
プロによるクリーニングで歯石や着色を取り除けば、見た目の清潔感が増すだけでなく、再感染のリスクを減らすことができます。
噛み合わせや被せ物の調整
根管治療後には被せ物や詰め物を装着することが多いですが、わずかなズレや高さの違いでも噛む力のバランスが崩れ、歯や顎に過剰な負担を与えることがあります。
その結果、再び痛みや違和感が出たり、炎症が悪化する原因にもなりかねません。
治療後に「噛みにくい」「違和感がある」と感じたら、我慢せず歯科医師に調整を依頼してください。
また、詰め物や被せ物は年月とともに劣化し、わずかな隙間から細菌が侵入する恐れがあります。
そうなると再感染のリスクが高まるため、定期的なメンテナンスや交換を受ける必要があります。
歯痛ケアには早期受診と適切な治療が大切
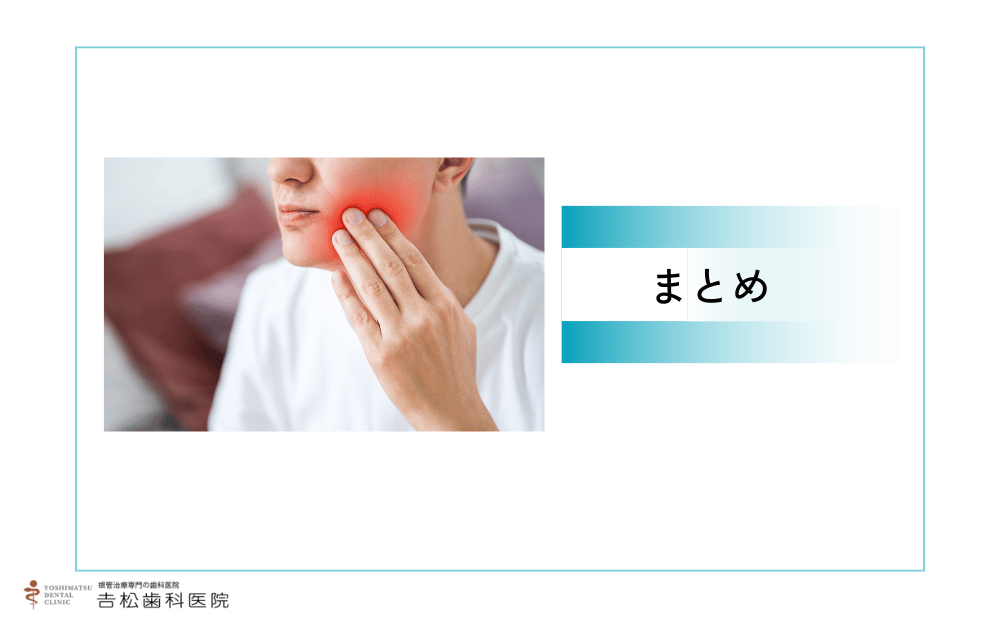
冷水で痛みが治まるからといって「そのうち治る」と放置するのは危険です。
歯痛の多くは虫歯や歯周病といった進行性の病気が原因であり、自然治癒はほとんど期待できません。
放置すれば炎症が広がり、抜歯やインプラント治療が必要になるケースも少なくありません。
違和感や痛みがあるときは自己判断せず、早めに歯科医院を受診し、適切な治療を受けましょう。
吉松歯科医院では歯科用CTやマイクロスコープなどの設備を導入し、安心して治療を受けられる環境を整えています。
セカンドオピニオンにも対応していますので、お気軽に下記よりご相談ください。







