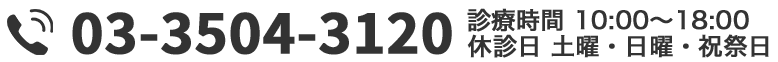
歯の神経を取る治療とは?治療の流れやその後のケアまで徹底解説
歯の神経を取る治療は「根管治療」と呼ばれ、虫歯や外傷によって歯の内部にある神経(歯髄)が炎症や感染を起こしたときに行われる処置です。
歯を抜かずに残すための最終手段でもあり、正しい知識を持って受けることで歯の寿命を延ばすことができます。
しかし、治療内容やその後のケアについて十分に理解していないと、不安や誤解を抱いてしまう方も少なくありません。
本記事では、歯の神経を取る必要があるケースや治療の具体的な流れ、治療後に気をつけたいポイントを徹底解説します。
港区で安心して根管治療を受けられる歯科医院を探している方は、下記の記事もご確認ください。
歯の神経を取る必要があるケース
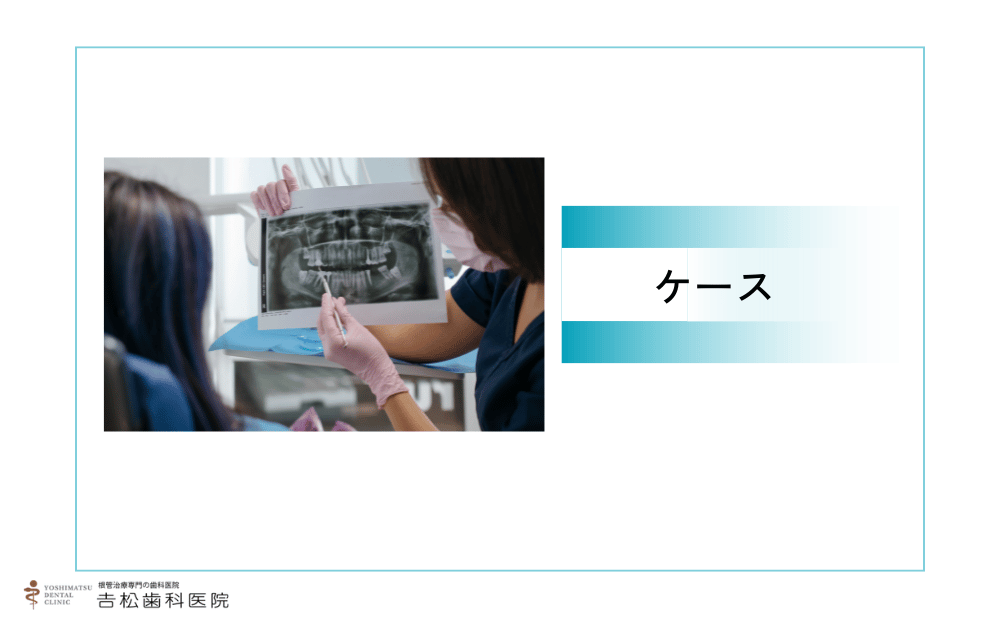
歯の神経を取る必要があるケースは下記のとおりです。
- 進行した虫歯による感染
- 歯の破折・外傷
- 歯髄炎の悪化
順番に説明します。
進行した虫歯による感染
初期の虫歯は歯の表面であるエナメル質にとどまり、適切な処置をすれば比較的簡単に治療が可能です。
しかし進行すると細菌は象牙質へと侵入し、さらに内部の歯髄(神経)にまで達してしまいます。
神経にまで感染が及ぶと、鋭い痛みや歯茎の腫れを引き起こし、自然治癒は期待できません。
この段階では神経を取り除き、根管の内部を徹底的に洗浄・消毒し、最終的に密閉する「根管治療」が必要になります。
もし治療をせずに放置すれば、歯の内部に膿がたまり、根の先から顎の骨に炎症が広がり、骨の吸収や顔の腫れを伴うケースもあります。
さらに全身に細菌が回って重症化するリスクもあるため、早期の治療が欠かせません。
根管治療について詳しくは下記も合わせてご覧ください。

歯の破折・外傷
転倒やスポーツでの衝突、あるいは硬い氷やナッツなどを強く噛んだ際に歯が深く割れてしまうことがあります。
一見すると小さな欠けに見えても、実際には歯の内部にまで亀裂が入り込み、神経にまで達していることがあります。
この場合、細菌が裂け目から侵入して炎症を起こし、やがて神経が壊死してしまうことも少なくありません。
内部で進行するダメージは外見からは分かりにくいため、「少し欠けただけだから大丈夫」と放置するのは危険です。
痛みが軽くても、しみる・噛むと違和感があるなどの症状が出たら、神経を取る治療が必要になることもあります。
吉松歯科医院では豊富な治療実績があり、歯を残す治療を得意としています。
詳しい実績は下記をご確認ください。
歯髄炎の悪化
虫歯や外傷が原因で歯の神経に炎症が起こることを歯髄炎といいます。
初期の段階であれば神経を温存し、部分的な治療によって歯を残すことが可能な場合もありますが、炎症が進行すると、冷たいものや熱いもので強くしみるだけでなく、何もしていなくてもズキズキと痛みが続いたり、夜間に眠れないほどの痛みが出たりすることがあります。
こうなると神経を保存することは難しく、やがて神経は壊死し、感染が歯の根の先や周囲の骨に広がる恐れがあります。
歯髄炎が悪化した状態を放置すると、治療が複雑化し、最悪の場合は抜歯に至ることもあるため、適切なタイミングで神経を取る治療を行うことが歯を守るためには必要です。
歯の神経を取る根管治療の流れ
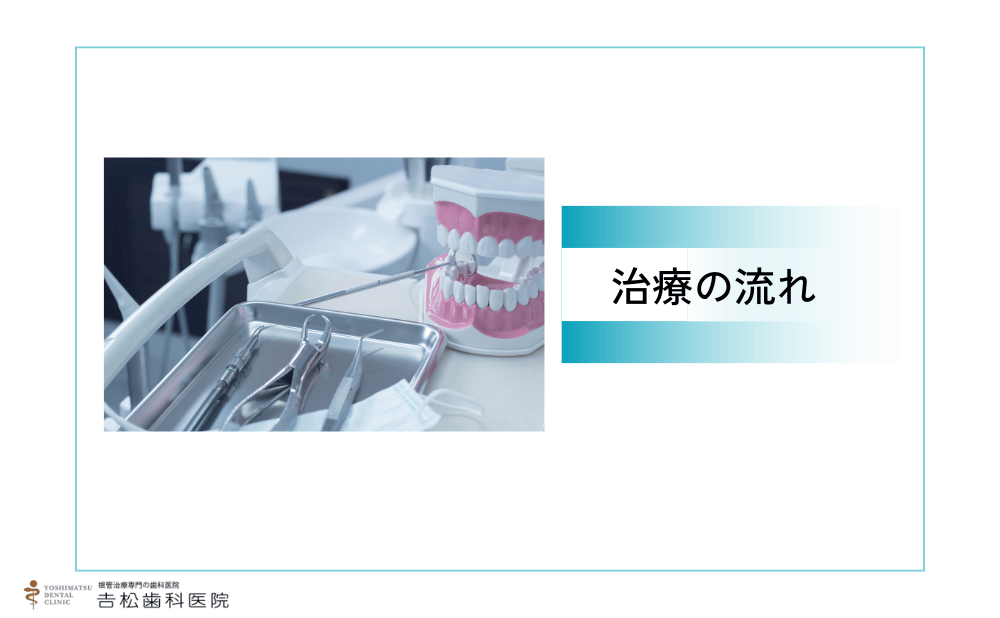
歯の神経を取る根管治療の流れは次のとおりです。
- 麻酔から神経除去までの手順
- 治療後の詰め物・被せ物
それぞれ解説します。
麻酔から神経除去までの手順
まず治療は局所麻酔から始まります。
しっかりと麻酔が効けば、治療中の痛みはほとんど感じません。
次に、歯に穴を開けて内部の神経や感染した組織を丁寧に取り除きます。
その後、根管専用の器具を使って内部を清掃し、細菌を徹底的に除去します。
薬剤を用いた洗浄を繰り返すことで、目に見えない細菌や感染源まで取り除いていきます。
治療後の詰め物・被せ物
根管がきれいになったら、再感染を防ぐために薬剤や充填材をすき間なく詰め込みます。
内部を密閉した後は、歯の形や機能を回復させるために詰め物や被せ物を装着します。
特に神経を取った歯は脆くなるため、強度を補うクラウンを被せることもあります。
最近ではセラミック素材を用いた被せ物も増えており、自然な見た目と耐久性を兼ね備えています。
歯の根管治療の症例紹介


抜髄、歯の中の神経をすべて取り除く治療の事を抜髄と言います。
標準的な診査診断では、歯の神経、歯髄に少しでも感染があると、全ての神経をとることが標準的な治療です。
しかし近年、マイクロスコープ、バイオセラミック系材料、歯科接着などが出て来て、従来では不可能であった事が、出来る可能性がある時代に入って来ました。歯の神経、歯髄は可能であれば、出来るだけ歯髄を残す事が歯にとって、とても良い事です。
歯髄を残すという事は、歯の血液供給など歯の栄養源が保たれる事です。歯髄の感染は、どこまで感染しているかは、経験的なイメージしかまだわかっていない為、確実に歯髄を残せる、残せないの診断が術前に行うことが出来ません。
治療中の神経、歯髄の状態、色や毛細血管が確認できるとか、根管内壁に生着しているなどの臨床写真で判断しています。
吉松歯科医院でも、歯髄の保護を行なって、症状がなく数年したらレントゲン上で歯の根の先の骨が吸収してる事から、抜髄処置に至ったなどの症例を経験しています。
また、成功例としては自発痛(何もしてなくても痛い)、打診痛(叩いて痛い)の症状があると虫歯の進行が歯髄まで感染してると診断され、抜髄の診断でしたが、海外の先生達の症例で成人でも断髄(一部分の神経だけを取り除き、残りの神経、歯髄は残す)治療を観てきたので、患者さんに急に痛くなる可能性がある事を伝えて、同意を得て神経の保護、一部分の神経、歯髄を取り除き、残りの歯髄を残す治療を2014年から実践しています。
小児歯科の分野では、断髄処置は、大学レベルでも行われていますが、成人では断髄処置は禁忌であると教えられてます。まだ不確かな事もかなりある為、アメリカとヨーロッパでも考え方が違い、自分の臨床経験が一番の頼りだと考えています。
この写真は、感染部を削合して行ったら、神経、歯髄が露出したためバイオセラミックで神経、歯髄を保護している写真です。
歯の神経を取る治療で気をつけたいポイント
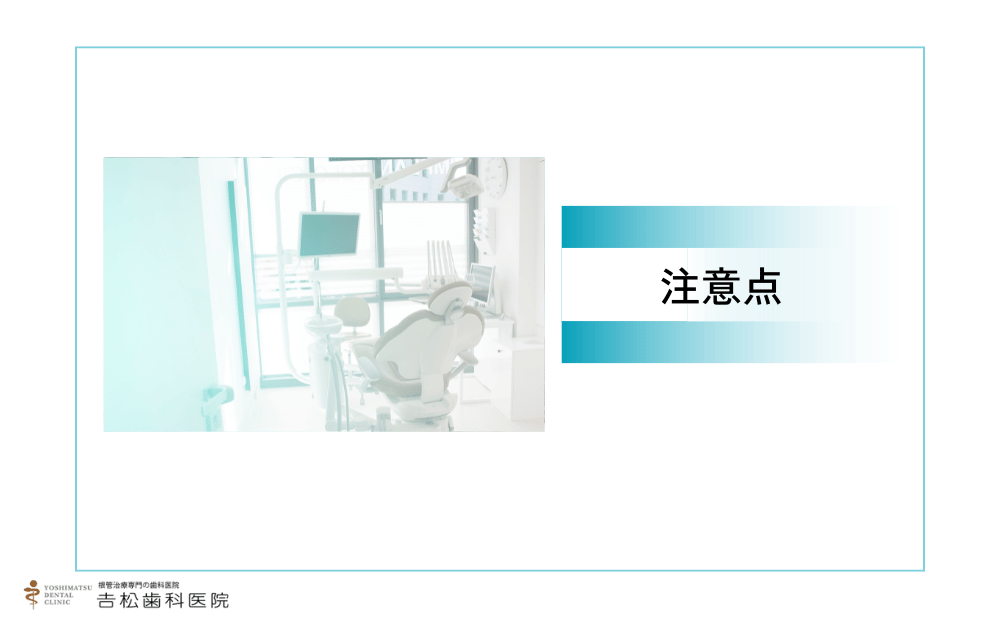
歯の神経を取る治療で気をつけたいポイントは以下のとおりです。
- 痛みや違和感の対処法
- 再感染を防ぐためのセルフケア
順番に解説します。
痛みや違和感の対処法
治療直後は麻酔が切れたあとに軽い痛みや噛んだときの違和感が残ることがあります。
これは数日で落ち着くことが多いですが、痛みが強い場合は鎮痛薬の使用も検討されます。
重要なのは、無理に硬いものを噛んだり、治療中の歯に負担をかけたりしないことです。
数週間経っても痛みが続いたり、腫れがひどくなったりした場合には、早めに歯科医院へ相談してください。
再感染を防ぐためのセルフケア
神経を取った歯は再感染しやすいため、セルフケアが欠かせません。
毎日のブラッシングはもちろん、フロスや歯間ブラシを使って歯と歯の間の汚れを徹底的に除去することが大切です。
また、治療後は仮詰めの状態で過ごすこともあるため、その間は食べ物が詰まりやすく注意が必要です。
定期的な歯科検診を受けることで、治療後の状態をチェックし、トラブルを早期に発見することができます。
歯の神経を取る治療は正しい理解と歯科医院選びが重要
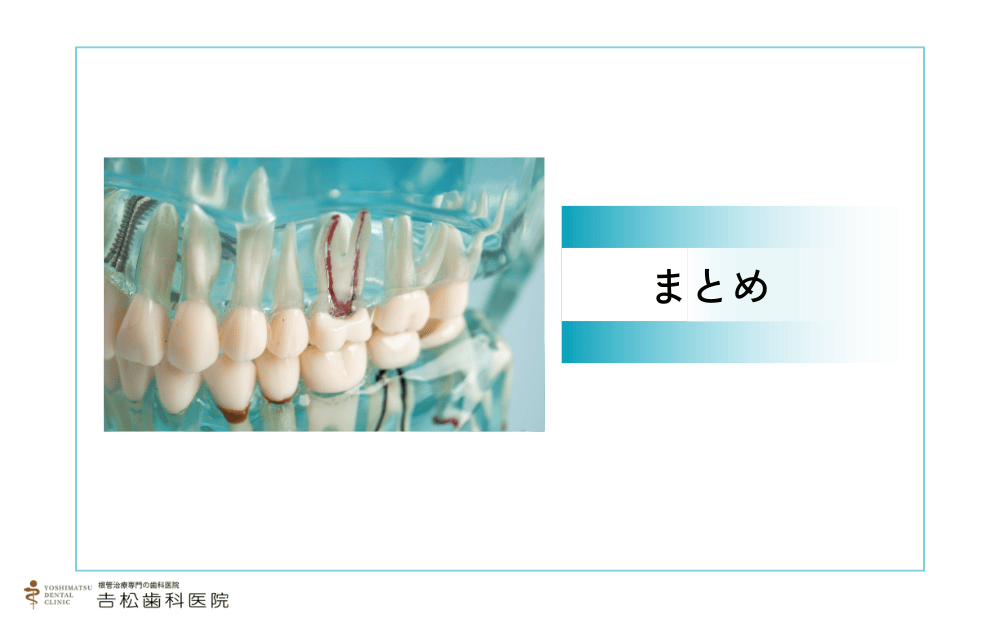
歯の神経を取る治療は、歯を失わずに残すための大切な手段です。
しかし、治療の難易度は高く、歯科医師の経験や設備によって結果が変わることもあります。
痛みや不安を抱えたまま放置すれば、最終的に抜歯に至るリスクも高まります。
だからこそ、信頼できる歯科医院での相談と、患者様自身の正しい理解が欠かせません。
吉松歯科医院ではアメリカの根管治療専門医が抜歯と診断した場合でも、歯を残せる可能性があります。
豊富な実績と丁寧な治療説明で、安心して治療に移っていただけます。
根管治療を検討している方は、まずはお気軽にお問い合わせください。








